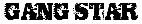【VERSUS】(映画)
【バズ・ミークス】(小説関連)
【裸ワイシャツ】(萌えカルチャー)
【バド・ホワイト】(小説関連)
【バレットウィッチ】(ゲーム)
【ハレルヤ、おれは飛べる!】(小説関連)
【パンチラ】(萌えカルチャー)
【ビッグ・ノーウェア】(小説)
【100万回生きたねこ】(猫)(絵本)
【FPS(First Person Shooter)】(ゲーム関連)
【BLACK】(ゲーム)
【ブラック・ダリア】(小説)
【プレデター】(映画関連)
【フロントミッション・オルタナティヴ】(ゲーム)
【ヘッドショット】(ゲーム関連)
【ホワイト・ジャズ】(小説)
■VERSUS
(映画)(全員が、戦う)

北村龍平監督のバイオレンスアクション映画。死者が蘇る森を舞台に、ゾンビ、脱獄囚、ヤクザ、殺し屋、処刑コップ(原文ママ)がバトルロイヤルを繰り広げる。
一応ゾンビ映画に該当すると思われるが、出てくる連中がどいつもこいつもゾンビなど屁とも思わない武闘派ぞろいであり(一部例外あり)、もっぱら彼ら同士が戦うことになる。中盤以降は主人公である「絶対に負けないヒーロー」と、謎めいた黒幕である「全てを知る不死身の男」の間に数百年に渡る因縁があることが明かされ、伝奇アクションめいた雰囲気になるが、基本的には森の中でイカれた連中がゾンビを巻き添えにしながら殺し合うというものである。
いかにも低予算な作りながら、格闘あり、二挺拳銃あり、チャンバラありと、ある意味で豪華なアクションが目白押し。焼肉屋でひたすら肉だけを食べるような感覚で、アクションだけをたっぷり詰め込んだB(ボンクラ)級映画である。「全員が戦う」という謳い文句に偽りはない。
特に主演の坂口拓はボクシングのプロライセンスを持っているそうで、格闘シーンが実にサマになっている。ビジュアルファンブックによれば彼はもともとプロ格闘家を目指していたが、中国人格闘家に手痛い敗北を喫し諦めたそうだ。
関連:【二挺拳銃】
■バズ・ミークス
(小説関連)(人物)
『暗黒のLA四部作』の登場人物で、本名はターナー・ミークス。“バズ”とは棍棒を振り回す擬音で、その名の通り警棒を振るっての荒事が得意。LA市警の元警官で、そこを辞めて後は大富豪やギャングのバッグマン(御用聞き)や揉み消し屋(フィクサー)として働いている小悪党。
『ブラック・ダリア』『ビッグ・ノーウイェア』『LAコンフィデンシャル』の3作に登場しており、そのうち『ビッグ・ノーウェア』では主人公の一人を務める。金が動機で大陪審によるアカ狩り捜査に加わるが、それとは無関係のところでギャングのボス・ミッキー・コーエンの情婦であるオードリーに横恋慕し、危険な恋愛に溺れていく。
劇中、バズは自分の行動を「愚かしくて、とち狂っていて、センチメンタルで、まさしく狂気の沙汰だ」と評しているが、『ビッグ〜』における彼の行動原理はまさしくそんな感じ。要領良く立ちまわれる小悪党なのに、どこかセンチメンタルな部分があり、他の登場人物とはやや毛色が違うように感じる。特に本編第3部「ウルヴリン」冒頭での彼の独白には胸が熱くなる。
映画版『LAコンフィデンシャル』にも登場しているが、こちらはほんの端役である。
余談だが、管理人は彼の姿を思い描こうとすると「クロウ-飛翔伝説-」に登場した質屋の親父「ギデオン」が脳裏に浮かんでくる。
関連:【クロウ-飛翔伝説-】 【ビッグ・ノーウェア】
■裸ワイシャツ
(萌えカルチャー)

文字通り、裸体にワイシャツのみを羽織った状態のこと。推定される状況は寝起き、入浴直後、情事の後など多彩。ワイシャツのサイズはなるべく大きめ(袖から指先が出る程度)であるのが望ましい。
体をすっぽりと覆い隠しつつも無防備な状態であり、着用者の信頼・親愛さを表すことができる。さらに「このシャツ、お兄ちゃんのにおいがするね。えへへ♥」的な萌えボイスとセットにすることでさらに効果が増す。
類似のものとして「裸エプロン」があるが、こちらは露骨に“媚びた”スタイルであり、上記のワイシャツと比べあざとさが先に出る。
 裸エプロン
裸エプロン色気よりも品のなさが強調されがちだが、着用者が「先にご飯にする? それともわ・た・し?♥」という具合におもてなし精神を発揮してくれるなら、その可愛さを引き出すアイテムとして存在価値がないでもない。
もうひとつの類似スタイルとして「裸ネクタイ」があるが、これは裸体を隠す効果が全くないため、根本的に異質と見るべきだろう。
 裸ネクタイ
裸ネクタイ裸エプロンよりもさらにあり得ないスタイルなため、日常の中の色気ではなく倒錯的なエロスの表現として用いられることが多い。
体を隠すのではなく強調させるためのアイテムなので、それなりに見栄えのよい肢体でないと返って逆効果にもなりかねず、その意味では上級者向けのスタイルといえる。
これと同様のものに「裸マフラー」があるが、こちらはネクタイと比較すると多少は体(というか局部)を隠しやすく、それが逆にエロティックさにつながっている。考えるに、この裸マフラーが「アホっぽくならずにエロくなる」ギリギリの下限ということができよう。
 裸マフラー
裸マフラーこの他にも「裸マント」「裸リボン」「裸にハイソックス」などがあり、「裸○○」のフェチズムは裾野が広い。時代とともにトレンドもに変遷しており、今後もまた新たなフェティシズムが生まれることと思う。
関連:【全裸忍者】 【パンチラ】 【萌えカルチャー】
■バド・ホワイト
(人物)(出典:LAコンフィデンシャル)
本名バド・ウェンデル・ホワイト。通称「バッド(悪党)・バド」。腕っぷしの強い荒くれ者のおまわり。
16の頃、アル中の父親が母親を殴り殺し、その死体が腐敗していく様をベッドに縛り付けられた状態で見続けていたというトラウマを持つ。そのため女性に暴力を振るう人間を異常に憎悪するようになった。自分の先輩刑事であるディック・ステンズラントを売ったエクスリーと対立することになる。
映画版『LA〜』ではラッセル・クロウが演じた。
関連:【LAコンフィデンシャル】
■バレットウィッチ
(ゲーム)

2006年にXbox360で発売された日本製TPS。
箒を模した銃「ガンロッド」を手にした魔女、アリシアが悪魔と戦いを繰り広げるというもので、通常の銃撃のほか各種の魔法(障害物を吹き飛ばす念動力、銃撃を防ぐ壁の生成など)を使った戦闘が特色。
操作性がぎこちない、理不尽に難しいなど問題点をいくつも抱えており、凡作以上か以下かは意見が分かれる。しかし見上げるように巨大なボスキャラや物理演算を駆使した破壊描写など、新世代ハードのパワーをうかがわせるゲームだったのは確かである。
ハードの黎明期という当時にしては十分遊べる出来であり、わけても魔法を使った戦闘はブラッシュアップ次第で化ける可能性も感じられたため、1作限りで終わったことを惜しむファンは多かった。
・キュートなアリシアさん
本作の魅力は実際のところ主人公であるアリシアさんによるところが大である。巨大な銃を手にした黒衣の美女というスタイルは美しさとカッコ良さが絶妙に溶け合っており、綺麗で強くてカッコいいおネーさんが大好きな人にとってはどストライクなキャラだった。
おネーさんといっても後の魔女キャラであるベヨネッタと比較すればまだ少女らしい部分もあり(劇中の情報を付き合わせると推定19歳だったはず)、DLCの女子校生コスも違和感なく着こなしている。それでいてアダルティな秘書コスでセクシー美女にも化けるし、まったくもって魔女はけしからんな! 俺が異端審問してやる!というようなヒロインであった。

 女子校生アリシアと秘書アリシア
女子校生アリシアと秘書アリシア女子校生コスはブラが透けてる上に当然のごとくパンチラするという、少々やり過ぎ感がある媚びっぷりだが、基本的には戦うヒロインとしてのクールさと可愛さをうまく融合したキャラクターデザインだと思う。
なお一部ファンから熱烈に望まれた「魔女っ子コス」は残念ながら出なかった。
・アメリカでのアリシアさん
日本の翌年にリリースされた北米版では一部のダメージ数値が修正されたほか、緊急回避中にもカメラ操作が可能になるなど操作性も改善され、日本のユーザーを羨ましがらせた。さらに特典のブックレットには描き下ろしのコミックを収録するなど、様々な意味で豪華なバージョンだったといえる。



だがシューター本場の壁はやはり高く、レビューサイトのスコアは10点満点中平均5点台という酷評に終わった。
もともと傑作とは言い難いタイトルではあったが、海外ではFPS/TPSにはマルチプレイがあって当然という風潮が強く、それを欠いたことで不利になったのは否めない。特に北米では前年、この世代の代表的TPSともいえる『Gears of War』が出ていたこともあり、バレットウィッチのユニークさよりも至らなさの方が目につく結果となったのではないだろうか。
後になって海外ゲーム業界のコラムで「みんなバレッチをクソゲー扱いしたけど、俺はそんな悪くないと思うよ」的な記事を読んだ気がするのだが、探してもみつからない。いや確かにあったんだよ。夢とかじゃなくて。
なお全くの余談であるが、2007年に米プレイボーイ誌上で企画された「2006年のビデオゲームの女性たち」というページで、我らがアリシアさんが和ゲー勢ではただ1人登場し、おヌードを披露していらっしゃった。

もちろん公式イラストではないが、そもそも公式に許可を取った上での企画だったのかが気になる。
関連:【TPS】
■ハレルヤ、おれは飛べる!
(小説関連)(出典:ホワイト・ジャズ)

暗黒小説『ホワイト・ジャズ』において、重要証人として保護されていたサンダーライン・ジョンソンの変死を報じた新聞の見出し。
彼はギャングと裏取引したデイヴ・クライン警部補(主人公)にホテルの窓から突き落とされ死亡するが、クラインはこれを彼が正気を失った末の投身自殺だったと捏造。サンダーラインが新興宗教にハマっていたこともあり、記者は独自のセンスを加味して上記のような見出しで記事にした。
重要証人がこともあろうに警官によって謀殺されるという「暗黒のLA」を象徴するドス黒いエピソード……のはずだが、サンダーラインが善良な市民というにはややイカれ度が高めであり、見出し文句が妙にノリのいいこともあって、一部のファンの間ではギャクワードとして扱われた。実際、印象的な言い回しの多い本作においても1、2を争う面白墓碑銘といえる。
なおクラインの上司であるエドマンド・エクスリーは事の経緯を察した上で、この投身自殺を「予定外のフライト」と称した。暗黒のLAにはひん曲がったユーモアセンスを持った人がいっぱいいる。
関連:【エドマンド・エクスリー】 【サンダーライン・ジョンソン】 【ホワイト・ジャズ】
■パンチラ
(文化)(萌えカルチャー)

文字通り、パンツがチラリと見えている状態のこと。推定される状況は突風、イタズラ、油断、ハイキックなど多彩。
パンチラが嫌いな男子はいないと断言できるが、下着の柄やシチュエーションについて細かいこだわりを持つ人が多いのも事実である。とくに見せ方(魅せ方)についても「パンチラ」と「パンモロ」を厳密に分けた上で「パンモロは無価値」と断じる人もいる。
 パンモロの例
パンモロの例いわゆるサービスシーンとしては古くから漫画・アニメなどでお馴染みだが、本項では主に家庭用ゲーム分野におけるパンチラ事情の変遷について記述する。なおここではパンチラ・パンモロの区別はせず、すべてパンチラとして扱うものとする。
(1)ドットからアニメ表現へ
(2)ポリゴンが広げた可能性
(3)飽くなき探求者たち
(4)多様化する嗜好
(5)縞パンの台頭
(6)海外事情とこれからのパンチラ
(1)ドットからアニメ表現へ
80年代、いわゆるファミコン全盛期からパンチラ描写は散見される。
サラッと言ったが、これはすごいことでもある。当時の小さなドットキャラクターでパンチラを表現するのは極めて困難であり、また容量の問題で見栄えのする一枚絵を出すのも一苦労だったからだ。
しかしそんな制限の中でもパンチラと呼ぶに足る表現を成し遂げた作品も少数ながらあり、ゲーマー少年たちに小さな幸せを提供していた。
 1ドットでパンチラを表現した『アタックアニマル学園』
1ドットでパンチラを表現した『アタックアニマル学園』 FC移植版『ドラゴンスピリット』。隠しコマンドでパンチラ
FC移植版『ドラゴンスピリット』。隠しコマンドでパンチラ80年代はファミコンからPCエンジン、メガドライブなど性能にかなり開きのあるハードが並存した時代だったが、そのうちPCエンジンは後にギャルゲーと呼ばれるようになる美少女ゲームを意欲的にリリースしており、その中でパンチラ等のソフトエロもごく普通に行っていた。
だが90年代に入りプレイステーション、セガサターンといった次世代ハードの時代になると、徐々にそうした表現に自主規制のメスが入るようになる。中でもプレイステーションはエロ描写に厳しく、絵としてパンチラを表現するのはほぼ御法度となっていた。
90年代末期はPCの18禁ビジュアルノベル、いわゆる「泣きゲー」のブームが起きつつあり家庭用ハードへの移植も相次ぐが、性的な描写は割愛またはエロすぎない程度にアレンジされ、パンチラしている絵などもアングルを変えたり、スカートに働く重力をねじ曲げるなどして修正されるのが常であった。同じ頃、ライバルであったセガサターンがX指定(18禁)のカテゴリーを設け、家庭用ハードとしては例のないエロ描写を解禁していたのとはえらい違いである。
しかしこの「ソニー規制」は徹底したものではなく、自社(SCE)開発のゲームについてはガバガバであった。特に顕著なのが「やるドラ」シリーズで、露骨なパンチラシーンがいくつも用意されていた。
 『ダブルキャスト』(1998)より
『ダブルキャスト』(1998)より 『季節を抱きしめて』(1998)より
『季節を抱きしめて』(1998)より自社ゲームのみ優遇するこのアンフェアなやり口に、ゲーマー少年たちは「ソニーはやり方が汚いな! でもまぁこれはこれで!」と義憤を募らせた。
余談だが『ダブルキャスト』のキャラクターデザインを担当した後藤圭二によれば、ヒロインの赤坂美月の服装は初期案はミニスカではなくもっと地味なものだったそうである。だが制作サイドから「もっと後藤さんらしいビジュアルに」と再考を促され、現在の形に落ち着いたという。初期案が通らなくて本当によかった、と胸をなでおろしたゲーマーもいたに違いない。
 ヒロインの赤坂美月。これでパンチラしなかったら暴動が起きていた
ヒロインの赤坂美月。これでパンチラしなかったら暴動が起きていたなおこの頃からゲームのパンチラ描写に新たなフロンティアが拓かれる。急速な進歩を遂げたポリゴンキャラクターのパンチラである。
(2)ポリゴンが広げた可能性
当時はいわゆるローポリゴンの時代であり、キャラクター描写のレベルもたかが知れていた。だが3Dゲームにおけるパンチラは、それまでの2Dゲームはおろか漫画、アニメでも存在し得なかった「可能性」を持ち込んだことでひとつの革命であった。
 『封神領域エルツヴァーユ』(1999)より
『封神領域エルツヴァーユ』(1999)より2Dのパンチラは、たとえ一瞬しか見えないものであっても「明確に見せる意図をもって描かれたパンチラの絵」が用意されている。これをもって「2Dのパンチラは全てパンモロに等しい」とする一部過激派の主張は狭量に過ぎるものの、一面の真理を突いてはいた。だがポリゴンで描かれたキャラクターのパンチラはそうしたお膳立てによらず、ゲームプレイの中で角度とか物理法則とかで“たまたま見えるかもしれない”ものであり、真の意味でラッキースケベ的な可能性を持ち込むことに成功した。これは2次元、3次元といった枠を超えたリアリズムへの到達でもあった。
なお厳しいとされるソニーの規制だが、こうしたポリゴンのパンチラはほぼノータッチであった。絵としてのパンチラはどう言い訳してもエロ以外の何物でもないが、3Dキャラクターがパンツをはいており、それが角度とか物理法則とかでたまたま見えるくらいなら自然の摂理の範疇であるため、規制の必要なしとされたと思われる。いい時代になったもんだとほくそ笑んだゲーマーもいたが、やがてそう単純な話でもないことを彼らは思い知らされる。詳しくは後述する。
(3)飽くなき探求者たち
2000年代に入り家庭用ハードがPS2、ドリームキャストに移り変わると、ポリゴンによるキャラクター描写も飛躍的に向上する。言うまでもなくパンチラ描写もネクストステージに到達した。
 『スパイフィクション』(2003)より
『スパイフィクション』(2003)よりそれまでパンチラ鑑賞に堪えるほどのポリゴンを使用したキャラクターは格闘ゲームなどごく一部のジャンルに限られていたが、ここに至ってRPGなど多くのジャンルがその恩恵を受けられるようになる。
ただしRPGなどは格闘ゲームのように常時激しい動きをするわけではないので、普通にプレイする分にはパンチラしないことが多い。そこで、どうにかカメラアングルを工夫してパンツを拝もうとする
彼らは「パンツァー」と呼ばれ一部の界隈で揶揄をこめつつ賞賛されたが、そんな彼らの前に立ちはだかったのが「暗黒パンツ」と呼ばれるメーカーの自主規制である。これは本来パンツが存在する部分を作らずに済ませるという一種の手抜きであり、この場合スカートを覗くとパンツのあるべき部分が真っ暗になっていることからそう呼ばれた。
ゲーム内のさまざまな場所でカメラアングルを試行錯誤したり、あるいは特定アクションの一瞬に目を光らせたりなど、パンチラ探求は時にただならぬ労力を必要とした。その挙句に「暗黒パンツ」という残酷な現実を突きつけられたパンツァーたちの心痛は察するに余りある。
(4)多様化する嗜好
「暗黒パンツ」は手抜きの謗りを免れないものだったが、技術の発展に伴い不自然さが目立つようになったせいか、次第に姿を消していく。一方でパンツ以外の可能性を広げようという試みも90年代から行われていた。例を挙げると「スカートの下にブルマ」「スカートの下にスパッツ(レギンス)」「スカートに見えて実はショートパンツ」などがそれである。
メジャーシーンにおける代表例は『ストリートファイターZERO2』で初登場した女性キャラ「さくら」であろう。セーラー服の女子高生でスカートの下はブルマという、カプコンにしては異例なほど媚びたキャラクターデザインであり、ゲーマー界隈に驚きをもって迎えられた。基本的には大人気のキャラクターではあったが「なんだよパンツじゃねーのかよ」と落胆したゲーマーも無論いた。
 『ストリートファイターZERO2』(1996)のさくら
『ストリートファイターZERO2』(1996)のさくら 『キングオブファイターズ'96』麻宮アテナ。こう見えてショートパンツ
『キングオブファイターズ'96』麻宮アテナ。こう見えてショートパンツブルマがエロアイテムとして市民権を得ていたのは後に教育現場からブルマが姿を消したことからも明らかだが、「パンツだと思った? 残念、ブルマでしたー♪」というシチュエーションに怒りを覚える男性も少なからずいることは強調しておきたい。
こうしたパンツ以外の可能性の模索はパンツァー達を落胆させるものであったが、さりとて大声で不満をぶちまけるのも世間体の上で憚られ、同好の志と慰めあうにとどめるのが常であった。
(5)縞パンの台頭
実のところパンツの色や柄について、男性ユーザーの好みはそこまで細分化されているわけではない。むしろ派手目なものだと「水着みたい」という理由で歓迎しない傾向もあるため「無地で白」が最大公約数的な支持を得ているのが現状である。ただし例外的に「縞パン(ボーダーショーツ)」のみは2次元のエロ文化の中で確固たる地位を占めている。
 縞パンの例
縞パンの例縞パンの台頭は90年代後半あたりだったように記憶している。人気の理由は「縞々がお尻のラインを立体的に表現できるから」とも言われるが、正確なところは不明である。
さておき、この縞パンの出現で危機感を抱いたのが「無地で白が最高だよ派」である。それまで圧倒的多数派だった彼らにとって「縞パンっていいよね派」の伸長は彼らの牙城を脅かすものとして警戒された。「白と縞はどちらがエロいか」はしばしば論争に発展し、時にはパンツァー同士で罵り合いになることすらあった。
 白パンツの例
白パンツの例だが振り返ってみれば、「無地で白のパンツ」は美学やこだわりによって生まれたものではなく「下着だから白が無難だろ、多分」という一種の思考停止によって量産されてきた面が少なくない。実際には白無地の下着はファンタジーの範疇に属するものだが、受け手も「パンツは白でしょ」と深く考えることなくそれを享受してきた。その意味では、縞パンの出現によって初めて白パンツはファンタジーという自分の立ち位置を正しく認識し、そこにこだわりと美学を込められるようになったと見ることもできる。
2016年現在では縞パンも白パンツもおおむね共存共栄しており、かつて一部で見られた両派の諍いもほぼなくなった。人と人は分かり合えるのだ、という好例であろう。
 人は分かり合える
人は分かり合える(6)海外事情とこれからのパンチラ
ところで日本のゲームでは露骨にパンチラを期待させるミニスカ衣装のキャラは珍しくないが、洋ゲーではあまり見られない。少なくとも日本で販売されるような大作では稀である。
 露骨に期待させる衣装の例(ただしレオタード)
露骨に期待させる衣装の例(ただしレオタード)海外といっても国によって理由は異なると思うが、巨大市場であるアメリカを例にとると性的描写のゾーニングが日本より厳しいこと、また「戦うキャラがヒラヒラのミニスカートはいてるのは変」というリアリズム重視の姿勢によるところが大であろう。
だが欧米のゲームでは成人向けカテゴリなら家庭用ハードでもセックスシーンまで描いているので、性的描写全般に否定的というわけではない。その点でパンチラはゾーニングの点で曖昧な立ち位置にあり、また「互いの合意によらない一方的なエロ」という点もまた歓迎されない要因かと思われる。
しかしミニスカコスでのパンチラが皆無かといえばそうでもなく、かつては超能力TPS『サイオプス:サイキックオペレーション』(日本発売・2005)で、それに近いものがありはした。
このゲームはクリア後に開放される「エクストラコンテンツ」で、劇中に登場するザコ兵士からボスキャラまで豊富なキャラクターのスキンを選べるのだが、そのうち女ボスの一人であるウェイ・リューはミニスカチャイナのコスがあり、角度とかポーズとかでパンチラが拝める。
 ボスとして登場時のウェイ・リューさん。この後怪物に変身する
ボスとして登場時のウェイ・リューさん。この後怪物に変身する ミニスカコス(黒ニーソ)はエクストラスキン限定
ミニスカコス(黒ニーソ)はエクストラスキン限定管理人の記憶では色は白だった気がするのだが…ひょっとして海外版と日本語版で違うのだろうか。いずれにせよ現在の洋ゲーではこうしたコスチュームはあまり見られない。
グローバル化によってこれまで日本国内でのみ消費されてきたエロジャンルも海外の目に晒されるようになってきたし、パンチラの在りようについても今後変わっていくかもしれない。
関連:【裸ワイシャツ】 【萌えカルチャー】
■ビッグ・ノーウェア
(小説)

ジェイムズ・エルロイ「暗黒のLA四部作」第2弾。アカ狩りの嵐が吹き荒れるロサンゼルスを舞台に、3人の男がそれぞれの事件に挑む。
3人の主人公が個々の目的の為に戦い、やがて狂気をはらんだ巨大な陰謀へと迫っていくという筋書きは、次作「LAコンフィデンシャル」でも踏襲されている。
関連:【暗黒のLA四部作】 【チャンピオンの朝飯】 【リステリン】
■100万回生きたねこ
(猫)(絵本)

「100万年もしなないねこがいました。100万回もしんで、100万回も生きたのです」という出だしで始まる絵本。作・佐野洋子。
自分だけしか愛さない自己完結した存在であった主人公が初めて誰かを愛し、死を迎えるまでの物語で「人はひとりでは生きられない」というテーマを逆説的に描いている。
生まれて初めて愛した人を喪い、悲しみのうちに死んで二度と生き返らなかったというラストは悲劇的ではあるが、悲しみの中に一抹の安堵があるのは、主人公の死が「誰かと寄り添って生きた末の終着点」だからだろう。輪廻の輪から外れた外道の存在だった主人公は、初めて誰かを愛したことで我知らずまっとうな生き物となり、生き返る力を失った。それが結局は愛した人と同じ場所へ還ることになった、という救いでもある。
創作において「永遠の命を持つ者」はしばしば愛する者を失ってなお生きねばならない哀しみの具象化として描かれる。その意味で本作は「永遠なる者」の救済の物語ともいえるだろう。

それはさておき、注目したいのは主人公がただひとり愛した「白いねこ」である。己が死を超越した存在であることを鼻にかけ、多くの猫にかしずかれる主人公に、ただひとりこの白猫だけは媚びない存在として描かれる。
たった1ぴき、ねこに見むきもしない白いうつくしいねこがいました。
ねこは白いねこのそばにいって
「おれは100万回もしんだんだぜ!」といいました。
白いねこは
「そう」といったきりでした。
主人公は繰り返しこの白猫のもとに足を運んで自分の偉大さをアピールするが、白猫の反応は毎回同じ「そう」である。会話する気ゼロ。「で?」とか「それが?」と返答をうながすなら多少は会話に発展しようが、「そう」じゃ言葉を返しようがない。拒絶よりも冷たい、まるで石のような無関心である。それでも主人公は白猫のもとに通い続け、懲りずにアピールを繰り返すのだが、毎回「そう」でブッた切られる。
最終的に主人公が口にしたのは「そばにいてもいいかい」という率直で素朴な一言であり、この言葉に対して白猫は初めて、「ええ」と――やはり淡白な反応だが――主人公を受け入れる。
見事なまでに完成されたクール系ヒロインと言えよう。
ツンとすましたキャラは非常に猫っぽくもあるが、同時にヒロインとしてもレベルが高い。ギャルゲーだったら攻略意欲がモリモリ湧いてくるキャラであり、ユーザー人気投票で上位に来るのは間違いないポジションである。
そんなところもこの絵本が長く愛されてきた理由……なわけないけど、管理人は好きである。
余談だが、これと少し似た題名の絵本で「100まんびきのねこ」というものがある。猫を飼いたいと思った老人がイイ感じの猫を探しに行ったはいいが、思った以上にたくさんの猫がついてきてしまい、さぁ困ったどうしよう、というお話。山野を埋め尽くす猫の群れは圧巻である。
それらの猫たちは最終的にバトルロイヤルで飼い猫の座をゲットしようとするが、リアルに考えると慄然となる話である。
関連:【三びきのやぎのがらがらどん】 【トリゴラス】
■FPS(First Person Shooter)
(ゲーム関連)(ジャンル)
 『Shadow Warrior』(1997)
『Shadow Warrior』(1997)ファーストパーソンシューター。えふぴーえす。洋ゲーにおける人気ジャンル「一人称シューター」の略称で、もっぱら銃を手にドイツ兵やテロリストやギャングやゾンビやエイリアンを殺戮して回る、純度の高い戦闘ゲーム。秒間にどれだけ描画するかの指標であるfps(frame per second)とは別。こちらは小文字表記が一般的。
同ジャンルを確立したといわれる『Wolfenstein3D』(1992)から数えると20年以上人気ジャンルとして君臨しているが、どの時代のFPSも「銃を撃つ」という大原則を踏襲し、操作方法も大きな変化がないことを考えると驚くべきことである。
 『Wolfenstein3D』(1992)
『Wolfenstein3D』(1992) 『Wolfenstein:The New Order』(2014)
『Wolfenstein:The New Order』(2014)本項では主に日本の家庭用FPSの変遷について記述する。
(1)その魅力
(2)市場の観点から
(3)日本と海外の温度差
(4)これからのFPS
(1)その魅力
FPSの魅力は「狙って撃つ面白さ」が根本にある。それはビデオゲームにとどまらずダーツや輪投げといったアナログな遊戯にも通じる直感的な楽しさであり、それに加えて一人称視点がもたらす臨場感が、大方のアクションあるいはシューティングゲームと比べて並外れた没入感を付与していた。
90年代から00年代にかけてコンピュータグラフィックの技術は日進月歩の勢いで進化していたが、その技術を惜しみなく取り入れることでFPSの臨場感は進化していき、時代の最先端を走るジャンルとして人気を不動のものにしていった。
また「どの時代のFPSも基本の操作はほぼ同じ」という点も人気の持続に一役買っていたと思われる。FPSはアクションあるいはシューティングだけでなくRPGやホラーなど多様なジャンルを内包しているが、いずれも操作系統はほぼ共通していることから入り込みやすいという利点があった。
一方「一人称視点で敵を撃ち殺す」という生々しい暴力性はグラフィックが拙い黎明期から指摘されており、アメリカでもたびたびメディアの槍玉に挙げられていたという。それでも過激なバイオレンスを求めるユーザーの声もまた根強く、その後のFPSでも多かれ少なかれ暴力描写は取り入れられるようになる。
 有志制作の『Brutal Doom』(2010)
有志制作の『Brutal Doom』(2010)FPSの暴力描写は後の日本市場においても問題となった。FPSの進出当初はユーザーを遠ざける障壁となり、ある程度普及してからはローカライズに伴う表現規制がユーザーを一喜一憂させることになる。
FPSの魅力は対人戦も大きなウエイトを占める。3次元空間をフルに活用して行われる銃撃戦は、反射神経だけでなくマップの構造を利用しての待ち伏せなど多彩な戦術を可能にした。
なおアメリカでFPSがブームになった90年代前半、日本では対戦格闘ゲームが大流行りだったが、格ゲーは次第に高度化して新規層が入りづらくなり、ブームの終焉と共に市場も縮小していった。FPSも当時は「スポーツ系」と呼ばれる高度なテクニックと反射神経を要するFPSが主流だったが、『Counter Strike』などのタイトルがそれよりも敷居の低いカジュアルな対戦スタイルを打ち出し、新規層の拡大に成功した。
この傾向は00年代後期、家庭用ハードという大きな市場が生まれたことでさらに加速していく。
(2)市場の観点から
家庭用機へのFPSの進出はすでに90年代から始まっており、Nintendo64の『ゴールデンアイ007』(1997)などのヒット作も誕生していたが、ターニングポイントとなったのは2001年にXboxに登場した『HALO』である。シングルプレイのアクションとしての完成度もさることながら、オンライン対戦が人気に火をつけ世界的なヒット作となった。
なおHALOは「2本のアナログスティックによる操作」を確立したタイトルでもあることから、現代に至る家庭用機FPSの直接の祖先ということができる。
 記録的なヒット作となった『HALO』
記録的なヒット作となった『HALO』この頃から家庭用機でも盛んにPCからの移植やオリジナルのFPS・TPSがリリースされるようになる。そして00年代後期、PS3・Xbox360というオンライン機能を標準搭載したハードが主流になると、この流れは一気に加速する。それまでPCゲームとは縁のなかった層にもFPSとオンライン対戦が身近なものになり、この新たな需要を見込んでPCを中心にしていたメーカーも次々と市場に参入。多くのFPSがリリースされることになる。
市場が賑わったのは確かだが、一方で弊害もあった。PCを中心に展開していたFPSも家庭用機移植を視野に入れて作られるケースが増えたため、ビジュアル面などで意図的に制限がかけられたり、ゲーム性そのものも家庭用ユーザーに合わせて簡易化されるなど、ある意味では“退化”を余儀なくされる面が少なからずあった。PCのFPSに限っていえば、この時期は一種の停滞期と見ることもできる。
家庭用FPSも良い点ばかりとはいえない。増大する一方の製作費は次第にジャンルの多様性を衰えさせていき、特に『Call of Duty4』の爆発的ヒット以降は多くのFPSが“CODフォロワー”になってしまうなど、FPS界隈に漂う閉塞感に先行き不安なものを感じたユーザーも少なからずいた。特に2010年にリリースされた『Medal of Honor』の新作が露骨なCODもどきになったことは多くのファンを落胆させた。
またこの時期は「FPS(TPS)にはマルチプレイが必須」という風潮が強く、本来シングルプレイにこそ味があるゲームにも無理やりマルチプレイが入れられることが多かった。当然その分のリソースを割かなくてはならないため、結果としてどっちつかずになってしまうケースも少なくなかった。
(3)日本と海外の温度差
FPSはアメリカを中心に海外では押しも押されぬ人気ジャンルであり、中国・韓国などアジア圏においても例外ではない。ただ日本だけはどうしたことかパッとしなかった。
全く知られていなかったわけではなく、『ゴールデンアイ007』は国内でミリオンヒットを記録し、Xboxの『HALO』も熱心なファンを獲得した。しかしFPSというジャンルを日本市場に広く認知させるには至らず、ゲーマーの中にも「野蛮な人殺しゲーム」と軽蔑的に見る人間が少なくなかった。
アメリカで爆発的なヒットを記録した『DOOM』が登場したのは1993年だが、日本でFPSが広く認知されるのは家庭用ハードの主流がPS3・Xbox360になってからであり、ざっと15年ほどのタイムラグがある。
とはいえ2007年にPS3・Xbox360で『Call od Duty4』が登場すると流れも変わり、大作FPSはおおむね好調なセールスを維持するようになる。しかし日本で史上最もFPSがもてはやされたこの時代、主流ハードでは和製FPSは一作もリリースされなかった。
海外大手と比較して予算や技術面でハンデがあったのは確かだが、日本の十八番であったはずのアイデア勝負すら仕掛けなかったわけで、やはり何らかの壁があったのだろうと思わされる。
制作側がドンパチFPS以外の切り口(例えば『PORTAL』のような)を見いだせなかったのか。あるいは上層部に大作FPSでないと売れないという思い込みがあったのか。いずれにせよこのジャンルにおいて日本はずっと蚊帳の外であった。

 制作中止になった和製FPS『Coded Arms Assault』
制作中止になった和製FPS『Coded Arms Assault』日本でFPSが主流になりえなかった理由は昔から様々に論議されてきたが、主に挙げられていたのは次の3つである。
1. キャラクターが見えないから
2. 日本は銃や軍事が身近じゃないから
3. 日本人は3D酔いする人が多いから
一番妥当な理由は(1)だと思われる。昔から日本のゲームはキャラクター性を大事にしてきたし、FPSはなくともTPSはそれなりに作られていたことからもそれがうかがえよう。遊ぶ側としても「キャラクターになりきる」よりは「好みのキャラクターを操作する」方を好む傾向があり、その点で一人称視点は、臨場感という長所よりも自キャラが見えないという短所の方が大きい。
例えば主人公がハゲマッチョのおっさんなのかミニスカニーソの美少女なのかはそのゲーム全体の雰囲気を左右するくらいの大きな問題だが、一人称視点ではその違いがほとんど出せない。またミニスカ美少女が主人公の場合、三人称視点なら自然にパンチラも拝めるが、一人称視点ではパンチラどころか姿すら見えない。これは特に「萌え」や「エロス」を売りにしようとする場合は論外ともいえる短所であった。

 日本製TPSの一例
日本製TPSの一例つまるところ「FPSは萌えやエロと相性が悪いジャンル」ともいえるが、そういう切り口が全くなかったわけではなく、過去には「視点を下に向けると自分のおっぱいが見える」というFPSも存在した。
 『Trespasser』(1998)
『Trespasser』(1998)ちなみにおっぱいにあるハートの刺青は色によってライフ残量が分かるようになっており、「おっぱいを見る」ことにゲーム上明確な意味が与えられている。
実利と実益を兼ねつつ「おっぱいが見たいんじゃない、体力の確認をしたいだけだ」と横で見ている友人にも自分自身にも言い訳ができるあたり、なかなか悪くないアイデアだと思うが……正直なところそこまで魅力的なアングルとは言いがたい。そもそも男性プレイヤーは“巨乳美女を見たい”のであって“なりたい”わけではないので、根本からすでにズレがあったと言わざるを得ない。
現在の日本のゲームは多かれ少なかれ「萌え」や「エロス」の導入がノルマ化している観があるが、その点でFPSは確かに日本向きではなかった。
(2)の「日本は銃や軍事が身近じゃないから」については、多少の影響はあったにせよ決定的かどうかは疑問である。FPS以上に「銃」にフィーチャーしたガンシューティングゲームは昔からゲーセンの定番であったし、ロボットアニメなどではごく普通に軍隊や戦争というテーマが扱われていた。
そもそもアメリカのような銃社会ではない国でもFPSはヒットしているわけで、銃が身近か否かは大きな問題ではないという気がする。ついでに言うと「日本でファンタジーRPGが人気なのは剣と魔法が身近だからか?」という逆説的な反論もあり、ゲームの嗜好と文化的な土壌の関連性はそう単純ではなさそうだ。
ただし「銃で人間を撃ち殺す」という暴力的なゲーム性に抵抗があったのは事実だろう。FPSが身近になった現在では想像しにくいが、90年代初頭まではこれほど露骨な形で暴力を遊戯化したゲームは少数だった。銃で戦うゲームはいくらでもあったが、一人称視点の没頭感はそれらと比較して「銃で敵を殺す」という行為を格段に生々しいものにしていたからだ。
大ヒットした『ゴールデンアイ007』では制作中に任天堂の宮本茂が「ゲームの終わりに病院で敵と握手するような演出を入れてはどうか」とアドバイスしたそうだが、当時の世相を考えれば分からなくもない話である。
(3)の3D酔いについても無視できない部分ではあるが、日本人のFPS嫌いは見た目の印象で敬遠するのが大半であり、触りもしないケースが多かったことを思えばこれも決定的とは言いがたい。
ただし一人称視点の視野角の狭さから窮屈な印象を受けるという指摘は昔から一貫してあった。ブラウン管TV(モニタ)が主流だった時代はゲーム画面のアスペクト比も4:3と横幅が狭く、FPSは今よりずっと窮屈な視界でのプレイを強いられていた。そうしたゲーム画面をゲーム情報誌などで見た人が「なんだかやってて辛そう」と感じたとしても不思議はない。
00年代後期あたりから次第にFPSが受け入れられるようになったのは、16:9と横幅が広い液晶モニタが普及したのも一因だったかもしれない。
なお実際の3D酔いへの対処法としては「前もって車酔いの薬を飲んでおけばOK」「ゲロ吐きながらプレイしろ。そのうち慣れる」といった案がネットで挙げられていた。またゲーム内オプションでX軸・Y軸の感度を変えられる場合は、X軸の操作感度を高くすることで3D酔いを軽減できるという説もある。人間の眼球は左右方向の動きが速いため、ゲーム内の視点移動がそれより極端に遅いと違和感を覚えて気分が悪くなる、というのがその理由である。
3D酔いの原因は今もはっきりしていないそうだが、もし乗り物酔いに近いものであるなら、睡眠を十分取って万全の体調で遊ぶのが一番無難な対処法になると思う。
(4)これからのFPS
家庭用FPSにはこれまでいくつかのブレイクスルーが存在した。第一のそれは『ゴールデンアイ007』による家庭用FPSの成功、第二は『HALO』のヒットによる更なる市場の拡大とツインスティックによる操作法の確立。第三は『Call of Duty4』の大ヒットによるカジュアルFPSの定着である。
COD4以降はこれといった変革に乏しくジャンル全体が停滞していたような感が少なからずあったが、近年になると『Rainbow Six:Siege』『Overwatch』といったマニアックな競技性重視のFPSでヒット作が生まれ、一方で『Shadow Warrior』『DOOM』といった爽快なシューティングに回帰する動きも出つつある。
FPSは長い歴史を持つジャンルだけにこれまで幾度となくマンネリ化が指摘されてきたが、今もゲーム業界全体でトップクラスの人気タイトルを抱えており、なかなかに息の長いジャンルといえる。
第二次大戦時のソ連軍で制式採用されたPPSh41短機関銃を設計したゲオルギー・シュパーギンは「複雑にすることは易しい。シンプルにすることは難しい」という言葉を残したが、FPSは芯の部分がシンプルな分普遍的な面白さがあり、時代に合わせた変化もしやすいということかもしれない。
現在はVRが次世代ゲームの可能性を開くものとして注目を集めているが、一人称視点がもたらす没頭感とシューティング要素はVRとの相性も良いため、いずれここからも新時代にふさわしいFPSが生まれることと思う。そんなわけで、まだまだ人気ジャンルとしての座は揺らぎそうにない。
関連:【芋スナ】 【危険なドラム缶】 【キャンパー】 【TPS】 【ヘッドショット】 【洋ゲー】
■BLACK
(ゲーム)

2005年にPS2・Xboxで発売されたFPS(日本語版はPS2のみ)。日本では一部の洋ゲー好きに知られるのみであるが、過激な破壊描写と歯ごたえのあるゲームバランスが高い評価を受け、一部に熱心なファンを獲得した。
日本ではこの“破壊”がやや過大に宣伝されたこともあり(目に映るもの全てが破壊可能であるような印象を与えた)、先行入手したユーザーからは「言うほど壊れねぇじゃん」という声も聞かれた。しかし破壊可能なオブジェクトが群を抜いて豊富なのは事実であり、PS2ではトップクラスの美しいビジュアル、丁寧に練られたゲームバランスもあいまって徐々に評価は高まっていく。
(1)特色
・銃による破壊の快感
・豊富な爆発系オブジェクト
・ストーリー
(2)欠点
・気の利かない部分
・日本語版パッケージ
(3)アタコーヨ
(4)その後
(1)特色
・銃による破壊の快感
“破壊系FPS”と通称されるとおり苛烈な破壊描写が売り。それも爆薬を設置したり戦車で砲撃したりといったものではなく、基本的には銃弾によって建物の内壁をぶち抜いたりコンクリートの柱を削ったりするわけで、プレイ感覚としてはより直接的に“破壊している”という感覚を味わえた。
 銃撃戦後のステージ
銃撃戦後のステージマズルフラッシュが網膜に焼きつく勢いで撃ちまくり、敵兵をバリケードもろとも粉砕する快感は本作独自の魅力であり、「銃」の持つ破壊の力をけれん味たっぷりに描き出したFPSともいえる。サウンド面でも重々しい銃声や敵に攻撃をヒットさせた際のくぐもった効果音などは当時のFPSと比べ頭一つ抜けていた。
見ようによっては劇中に登場する銃こそ『BLACK』の真の主人公ともいえ、それは北米版パッケージ裏にある「ALL GUNS BRAZING」のコピーにも如実に現れている。

ついでに言うとタイトル前のオープニングデモはストーリー背景などは一切語られず、各種の銃の射撃やリロードのムービーに終始している。やたら美麗なグラフィック、舐めまわすようなカメラアングルなど、銃へのフェティッシュな愛情が感じられる代物だった。
ただ銃のディテールはリアリズムを追求しているわけではなく、例えばAK47は装弾数が60発だったり、排莢口やコッキングレバーが逆になっていたりする。ただし装弾数の多さは敵の耐久力の高さに合わせたものであり、排莢口については薬莢の排出を見せる演出の一環であるため、何も考えずにそうしているわけではない。
・豊富な爆発系オブジェクト
「危険なドラム缶」に類する爆発系オブジェクトが多いのも特徴で、ドラム缶の焚火やクーラーの室外機など、普通なら爆発しそうにないものも銃弾を撃ち込めば爆発を起こす。RPGを撃ってくる敵兵も倒すとなぜか爆発する。特筆すべきはステージ5「ナズラン製鉄所」にある巨大なタンクだろう。かなり遠方にあるのだが、RPGを撃ち込むとこれも大爆発を起こす。


 Youtubeより
Youtubeより『BLACK』のミッションは大半が秘密作戦(Black Operation)という設定だが、どこが秘密作戦だと言いたくなるほど目に余る破壊っぷりである。またステージによっては地雷が敷設されているが、複数が等間隔で配置されているため、端のひとつを爆発させるとドミノのように連鎖爆発を起こして敵を巻き込む。真面目に考えると置いたやつアホなの?という感じだが、こうした無分別な爆発も『BLACK』らしさといえる。
当初期待(=勘違い)されたほどではなかったにせよ“破壊”のカタルシスをとことん追求したFPSであり、今日にいたるまでフォロワーのない孤高の名作としてFPS史に名をとどめている。
・ストーリー
物語は命令違反で拘留されている主人公(ケラー軍曹)が取調官に事の経緯を説明するというもので、過去を振り返りながら大物テロリスト「レノックス」の足取りを追うというものになっている。『Battlefield3』(2011)のキャンペーンと同じ方式だが、BLACKの方は率直に言って出来が悪い。取り調べが進むにつれて主人公の精神状態が不安定であることが示唆されるが、それを抜きにしても話の筋が分かりにくいため感情移入しづらい。
とはいえ実写ムービーを使用した演出は渋く、取調官の台詞「偶然なんてどこにもないんだよ、軍曹」は2ch家ゲー板のBLACKスレでプチ流行した。
(2)欠点
・気の利かない部分
ハイクオリティなアクションゲームであることは疑いない『BLACK』だが、細かい所で「気の利かなさ」みたいな欠点が結構あったりする。その最たるものが「チェックポイントでセーブできない」という点だ。
セーブできるのはステージクリア時のみに限られ、道中を無駄にしたくなければ最低1時間は腰を据えてプレイすることが求められた。時間のない人には少々厳しい話である。
例外的に最初のステージだけはクリアまで10分程度と短く、かつ売りとなる破壊描写も十分に盛り込まれていたため、BLACK中毒者は多忙な日々においても寝る前にステージ1だけをプレイし、無聊を慰めていたといわれる(例:管理人)。
また難易度NORMALをクリア後に再度NORMALで始めると、全ての武器が銀色になって弾数が無限になる「シルバーウエポンモード」になるのだが、これはOFFに出来ない。もう一度新鮮な気持ちでNORMALに挑みたくても「遠慮すんな、ホラ持ってけ!」とばかりにチート武器にされてしまうのだ。正直申し上げて大きなお世話である。
敵の耐久力が他のFPSと比べて高いことも欠点として挙げられたりするが、それに見合うよう弾の装填数も多く補充も容易なため、特に理不尽というわけではない。「とにかく撃ちまくりたい。それもできるだけ長く」というタイプの人間(例:管理人)からすれば、敵一人にマガジン1本分ブチ込んでもOKなバランスはむしろ魅力でさえあった。
もっとも繰り返しプレイするうちに自然にヘッドショットを狙えるようになるため、耐久力の高さを好まない人にとっても大した問題ではなかったともいえる。
・日本語版パッケージ
日本語版パッケージの裏には「全てのものが壊れる」「迂回や小細工は無用、戦火に飛び込み撃ちまくるのがBLACKスタイル」と書かれているが、両方とも嘘っぱちである。破壊可能なオブジェクトが多いのは確かだが“全て”が壊れるわけではない。さらに「戦火に飛び込み撃ちまくる」というのは普通のFPSと同様、本作においても自殺行為である。
パッケージの制作に関して、おそらく本国のEAとEAジャパンとの連携に不備があったのではないかと思われる。
(3)アタコーヨ
劇中で敵兵が頻繁に発する「アタコーヨ」と聞こえる台詞はプレイヤーの脳裏に刻まれ、敵兵そのものの呼称、ひいては『BLACK』を象徴する単語のひとつとなる。
本作の舞台からしてロシア語と思われるが、正確な意味は不明。だが過去にYahoo!知恵袋で質問した人間がおり、それに寄せられた回答では「英語と同語源の『アタック』と関係のある単語と推測します。アタコヴァーチ(突撃する)という動詞があり、その活用形のどれかが『アタコーヨ』と聞こえるのかも知れません」とのことである。
(4)その後
オン・オフ問わずマルチプレイがないというハンデがありながら本国アメリカでも好評であり、続編を匂わせる情報が出たこともあったが、結局これ1作のみで終わっている。英語版Wikipediaによれば「BLACK2」の計画もあったそうだが、パブリッシャーのEAと折り合いがつかず立ち消えになったらしい。
その後、中心的デザイナーだったStuart Blackと、BLACKに携わったスタッフは精神的な後継作である『Body Count』の開発に取りかかるが、途中でStuart Blackは退社。そのせいかどうかは知らないが、2011年にPS3・Xbox360でリリースされた『Body Count』はレビューサイトの評価が10点満点中5点台と散々な結果に終わり、BLACK伝説が蘇ることはなかった。なお日本では未発売である。
 『BLACK』と『Body Count』のパッケージ比較
『BLACK』と『Body Count』のパッケージ比較結局1作のみで終わったBLACKだが、2016年現在でも本作ほど「銃による破壊」に重点を置いたFPSは稀であり、じっくり腰をすえて攻略する“アクションゲームとしてのシングルFPS”となるとさらに稀少である。昔も今もFPSの主流は競技性重視のマルチプレイシューターだが、またこういう骨太なFPSで遊びたいと願うゲーマーは管理人だけではないだろう。
関連:【危険なドラム缶】 【FPS】
■ブラック・ダリア
(小説)
1947年のロサンゼルスで、黒いドレスをまとった女が惨殺死体で見つかった。捜査は進展を見せずやがて忘れられようとするが、LA市警の刑事「ミスター・アイス」ことバッキー・ブライチャートは独力で捜査を続ける。
アメリカ犯罪史に名高い未解決事件「ブラック・ダリア事件」を題材にした小説で、ジェイムズ・エルロイの看板となる「暗黒のLA四部作」の第一弾。2006年に映画化。
関連:【暗黒のLA四部作】
■プレデター
(映画関連)

B級SFアクション映画の分野で根強い人気を誇る宇宙の狩人。
(1)概要
(2)カプコン製AVPの思い出
(3)コミックのプレデター
(4)プレデターは悪くない!
(1)概要
高度なテクノロジーを有しながら強靭な肉体を持ち、野蛮な狩りに興じるという斬新な宇宙人像を打ち出した。基本的には人間の脅威となる役どころだが、非武装の相手や妊婦は殺さない、敵であっても強者には敬意を払うという古風な戦士めいた価値観を持つことで株を挙げ、SFモンスターの中で独自の立ち位置を確立する。
また自分の武器を敵に奪われてピンチに陥ったり、ジェスチャーで意思疎通するなどの愛嬌も魅力のひとつであろう。特に映画3作目『エイリアンvsプレデター』以降はその傾向が強くなり、話せばわかる…というか話せなくともジェスチャーで何とかなりそうな気がするほど身近な存在(?)になった気がする。こうした馴れ合いともとれる傾向をよしとせず、プレデターはもっと孤高であるべきとする意見もある。
また特徴的な武器・装備類が多数登場するのも魅力といえる。腕部に装着したリストブレード、エネルギー弾を発射するショルダーランチャー(プラズマキャスター)が代表的だが、この他にも投擲武器のスマートディスクや捕獲用のネットランチャーなどなど、シリーズを追うごとにその数は増えている。いずれも殺傷効率第一の破壊兵器ではなく、狩人または戦士というスタイルにふさわしい蛮性を備えており、プレデターを特徴づける上で大きな役割を果たしている。

 リストブレード(左)とスマートディスク
リストブレード(左)とスマートディスクなお姿を消すクローキングデバイス(光学迷彩)、爆発物を内蔵した多機能コンピュータも彼らのマストアイテムである。爆発物の威力の凄まじさは彼らのテクノロジーの高さをうかがわせるが、何かのはずみで誤作動を起こしたりはしないかと見ていて不安にならないでもない。幸い、映画版では今のところそうした悲劇は起きていない。
(2)カプコン製AVPの思い出
2004年公開の『エイリアンvsプレデター』は、プレデターの一人「スカー・プレデター」が主人公のレックス(人間♀)と共闘し「異形のヒーロー」としてのイメージを強く印象付けた。中でも終盤クライマックス、クイーンエイリアンの隙を突いてスピアの一撃を喰わせる一瞬のカットは今でもアクション映画好きの間で語り草になっている。

 キャアアア! スカーさん素敵!
キャアアア! スカーさん素敵!だが日本のゲーマー層の間では、それより前から「ヒーローとしてのプレデター像」は一般化していた。その理由はカプコン制作のアーケードゲーム『エイリアンvsプレデター』のヒットである。
 カプコン製『エイリアンvsプレデター』(1994)
カプコン製『エイリアンvsプレデター』(1994)これはプレデターと人間のサイボーグ兵士がエイリアンと戦うベルトスクロールアクションで、そのうちプレデター勢は映画の1、2をモチーフにした「ウォリアー」と「ハンター」が登場していた。
 登場人物の皆さん
登場人物の皆さんウォリアーは使いやすいバランス型、ハンターはやトリッキー型とそれぞれ異なる戦闘スタイルながら、優れたジャンプ力や高性能の突進攻撃など、「人類を超越した異形の戦士」というポジションにふさわしい強さを発揮していた。
ちなみに人間側のプレイヤーキャラは半身を機械化した「ダッチ・シェーファー」、紅一点の「リン・クロサワ」の2人。ダッチの名は映画1作目の主人公と同名だが、関連は不明である。
 名台詞
名台詞ステージ幕間では彼ら2人とプレデターたちのやり取りが挟まれるが、本作のプレデターは片言ながら普通に会話ができ、映画でお馴染みの「録音した音声で会話っぽいやり取りをする」演出は存在しない。
分かりやすさを重視しての判断と思われるが、結果としてそのカタカナ喋りはプレデターの印象をより親しみやすいものにした。また、オープニングデモにおける「狩リノ・時間ダ」という台詞は宇宙の狩人というプレデターのイメージを決定づけた。
この作品はプレデターのゲームとしては貴重な日本産であると同時に、ベルトスクロールアクション史に残る傑作でもあったが、権利関係からいかなるハードにも移植されていない。現在、正規の方法でプレイする手段は基盤を買う以外なく、ゲーム史的に大きな損失だと思われる。
なおAVPのゲーム化はこれが初めてではなく、アメリカでは1993年にSNES(スーパーファミコン)とゲームボーイで同名の作品がリリースされている。
 スーパーファミコン版。旋風脚とか使う
スーパーファミコン版。旋風脚とか使う ゲームボーイ版。探索系アクション…?
ゲームボーイ版。探索系アクション…?SNES版はベルトスクロールアクションであり、上記のカプコン版に近いといえなくもない。これらは日本でも発売されたそうだが、知名度はいま二つくらいではなかろうか。
海外では後に植民地海兵隊・エイリアン・プレデターの三者を選択できるマルチプレイFPS『Aliens vs Predator』シリーズや、時代を超えて人間狩りを行う『Puredator:Concrete Jungle』などが作られているが、日本ではカプコン版以降音沙汰なしである。



 うらやましいラインナップだ
うらやましいラインナップだこれらは日本で発売されていないものがほとんどであり、英語版の購入が普通だったPCゲーマーはともかく家庭用機ユーザーにはなかなか手を出しづらいものだった。こうしたローカライズの不遇はおおむね日本における洋ゲー市場及びプレデター市場の小ささに起因するものであり、「日本でもプレデターがミッキーマウス並みに人気があれば…」と無念がるユーザーも一部にはいた。もっともこれはゲームに限った話ではなく、コミックについても同様であった。
(3)コミックのプレデター
アメリカでは80年代末期から盛んにプレデターのコミックが刊行されており、エイリアンvsプレデターなど後に映画に逆輸入されるシリーズも生まれている。だが、翻訳され日本で販売されたのは『バットマンvsプレデター』など一部に限られる。
 ビクターエンタテインメント出版『バットマンvsプレデター』(1994)
ビクターエンタテインメント出版『バットマンvsプレデター』(1994)これはゴッサムシティを恐怖に陥れる「姿なき殺人者」にバットマンが挑むというもので、設定としては映画2作目に近い。バットマンは持ち前の推理力でプレデターに迫るも、そのケタ外れの戦闘力に圧倒され重傷を負ってしまう。しかし『ダークナイト・リターンズ』の対スーパーマン戦を思わせる重装備でリターンマッチをかけ、辛くも勝利を納めるという筋書きだ。

プレデターの描写は「非武装の人間は殺さない」という部分はイマイチ徹底されてない感があるが、録音音声での会話などツボは押さえている。今ではレアな代物だが、プレデターファン、バットマンファンのどちらも楽しめる出来だと思う。
 つよそう
つよそうまた本筋とは関係ないが、バットマンがプレデターを野球バットで殴り倒し「やあ、私だよ。“バットマン”さ」とひどいジョークをかますのも本作の魅力といえる。
近年ではアメコミの映画化が相次いだこともあり、多くのアメコミが邦訳されている。この流れでプレデターのコミックも復刻・邦訳してほしいと思うファンは管理人含め大勢いるはずだ。
(3)プレデターは悪くない!
まったくの余談ながら、かつて2chの「『プレデターは悪くない!』スレ」ではプレデターの日記という設定で一人称のSSが執筆されていた。
内容は成人して間もないプレデターの「俺」が猟友会に入り狩猟生活をエンジョイするというもので、リストブレードマニアの「ケンジ先輩」、寡黙なベテランの「オオタさん」、無鉄砲な後輩「マサフミ」など、愉快なメンバーたちを通してプレデターたちの日常が描かれていた。中盤ではオオタさんが地球で軍隊と戦った末に爆死したり、マサフミも同じく地球で片腕を失う重傷を負ったりなどどこかで聞いたような話も挿入され、スレ住人を沸かせた。
何かと叩かれがちなスレッド内連載にも関わらず好意的な評価を得ていたが、「俺」がエイリアンクイーン2匹がいる惑星で窮地に陥り、仲間2人と反撃を期したところで更新が途絶えた。
まさしく「日記はここで終わっている…」というバッドエンドを想起させるものであり、再開を望む声も強かったが、今にして思えばそのB級っぽさも含めて予定通りの幕引きだったのではないかと思える。
SFモンスターの一方の雄であるエイリアンは「異邦人(Alien)」という語に宇宙生物というイメージを上書きしたが、プレデターが「捕食者(Predator)」という語のイメージを変えたかどうかは定かではない。だが日本のB級アクション好きの間においては、プレデターとは醜いけどカッコいいアイツのことであり、一般的な意味での捕食動物や軍用無人機RQ-1プレデターを指すものではない。
映画5作目『プレデターズ』からかなり年月が経ったが、またヤツらにスクリーンで会いたいものだ。そして今度こそ日本でミッキーマウスを凌ぐ人気者になり、浦安あたりにプレデターランドをおっ建ててくれればと思う。
■フロントミッション・オルタナティヴ
(ゲーム)

1997年にスクウェア(現・スクウェアエニックス)が開発したロボット戦略SLG。ターンベース制のSLG『フロントミッション』シリーズのスピンアウトであり、当時まだ珍しかったリアルタイムシミュレーションとして制作された。
シリーズの主役たる二足歩行兵器「ヴァンツァー」の前身である「WAW(ヴァンドルング・ヴァーゲン)」が初めて実戦投入されたアフリカ戦線を舞台にしており、物語的にはフロントミッションの正史に連なる作品である。ただしゲームシステム的には異端の存在であり、その後もこの系統の続編は一切作られなかった。
だがフルポリゴンで描き出された戦場で敵味方のWAWが砲火を交える様は当時としては迫力にあふれており、ビジュアルの面では抜きんでた魅力があった。接敵して戦闘になるとプレイヤーは基本見守るだけになるが、WAWが手にした盾で敵の砲撃を防いだり、バーニアを噴射してのサイドステップで敵弾を回避したりなど、豊富なアクションは見ているだけでも飽きなかった。
 移動の場面
移動の場面ゲームプレイでは戦闘よりも移動している時間の方がずっと長いのだが、舞台となるアフリカの砂漠・森林の描写もまた秀逸であり、その中をいかにも兵器然としたロボットが進軍する様は泥臭い魅力に満ちていたといえる。その手のビジュアルが好きな人間にとっては一種の鑑賞ソフト的な魅力があった。
当時スクウェアのゲームはファイナルファンタジーを始めプリレンダリングムービーの美麗さがもてはやされていた。だが本作はそういったムービーに頼らずポリゴンのみで目を見張るような臨場感を実現しており、ローポリゴンの美術という点では当時1、2を争うレベルにあったのではないかと思われる。これらのビジュアルが装甲騎兵ボトムズなどリアル系ロボット好きから熱い支持を受け、少数ながら熱心なファンを獲得するに至る。
ただし、本作は単なるロボットものにとどまらないニッチな要素もまた備えていた。
・LGBTに切り込んだシナリオ
本作の物語はアフリカの内戦に大国や軍事企業の思惑が絡んでくるというシリアスな作風だが、その裏に奇妙なほど“性”に関連する要素が盛り込まれている。WAWの装備品の名称は武器類は性器の隠語、シールドは避妊具の隠語から来ていると聞いたことがあるが、そうした小ネタ以上にプレイヤーに衝撃を与えたのは、登場人物に同性愛者やトランスジェンダーが存在し、それがメインシナリオにも関わってくる点である。
主人公マッコイが指揮する第一小隊のメンバー「ダル・ファーフィー」は、劇中で彼の口から同性愛者であること、そしてマッコイに想いを寄せていることが語られるが、本人にそれを伝えることなく彼をかばって戦死する。このことをめぐってマッコイと彼の相棒であるブルース(彼はファーフィーから秘密を打ち明けられた一人である)の間にいさかいが起きるが、そこに仲裁に入った補給小隊の紅一点・チャミリが、話の流れで「自分が性転換した元男」であることを打ち明ける。
マッコイは混乱しつつも「性の多様性」を受け入れるが、プレイヤーの多くが彼のように柔軟に対応できたかは不明である。

 ファーフィー(左)とチャミリ
ファーフィー(左)とチャミリこの一連のイベントは「ファーフィーがブルースやチャミリに自身の秘密を打ち明ける」→「ファーフィーがマッコイをかばい戦死する」→「マッコイとブルースの口論をチャミリが仲裁し、カミングアウトする」という順番になっている。だが管理人は何を間違えたのか、最初の「ファーフィーの告白」を見ないままその後のイベントに突入してしまい、「ファーフィーの戦死の衝撃も覚めやらぬうちに彼がゲイであると爆弾を投下され、畳みかけるように紅一点のチャミリが元男だと明かされる」というコンボを喰らう羽目になった。
このあまりに衝撃的すぎる展開は当時の管理人の許容量を超えており、「一体誰がこんな展開を望んだんだ!?」と怒りすら感じ、折に触れて「ファーフィーが“実は女の子でした”とかの方がみんな幸せになれたんじゃないのか」と述べてきたが、今日に至るまであまり同意は得られていない。
何にせよ90年代当時は今ほどLGBT(レズ・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー等の性的少数者)への理解度は低く、そこに来てこのようなテーマを扱うのはリスキーだったはずだが、これもまた本作のもつ反骨心の表れだったのだろう。
 当時のゲーム雑誌の記事より。彼女はヒロインではなかった…
当時のゲーム雑誌の記事より。彼女はヒロインではなかった…21世紀現在では海外ゲーム業界でLGBTへの配慮が進みつつあるし、その意味で本作は20年近く時代を先取りしていたといえるかもしれない。
思い返せば、当時のスクウェアは『バハムートラグーン』『ゼノギアス』『レーシングラグーン』のように挑戦的あるいは挑発的といえるようなゲームをしばしば世に送り出しており、制作者の個性を強く打ち出す作風が許容されていた感がある。本作もまたそうした尖った作品群のひとつに数えられるが、前述のゲーム同様、一定の支持は受けつつも続編は作られなかったあたり、やはりニッチ需要を満たすようなゲームには厳しかったようである。
余談だが、フロントミッションシリーズは2003年に一部の公式設定が見直され、ヴァンドルング・ヴァーゲンが「ヴァンダー・ヴァーゲン(Wander Wagen)」へ、ヴァンドルング・パンツァーも「ヴァンダー・パンツァー(Wander Panzer)」、へと名称が変更されている。幸いオルタナティヴの存在そのものが抹消されるということはなかったようだ。
とはいえ現在の同シリーズは酷評に終わった『フロントミッション・エボルヴ』(2010)を最後に休眠状態にあるため、どのみちオルタナティヴが再び日の目を見ることはなさそうである。
■ヘッドショット
(ゲーム関連)
人体最大の急所・頭部への攻撃を指す語。FPS/TPSでは必須の要素であり、同ジャンルの「狙い撃つ面白さ」を最も端的に表した要素である。現代ではテンポの速いスポーツ系シューターでも立ち回り重視のリアル系シューターでもほぼ例外なく取り入れられている。
ただし『DOOM』など最初期のFPSでは照準に高低の概念がなかったため、ヘッドショットが採用されたのはポリゴン技術の導入以後と思われる。英語版Wikipediaによれば、商業のソフトで最初にヘッドショットを採用したのはNintendo64の『ゴールデンアイ007』(1997)だそうだ。(Wikipedia - Critical_hit#Headshot)
以下、ヘッドショットに関するあれこれを列挙する。
(1)現実的な観点からのヘッドショット
(2)ゴア描写へのこだわり
(3)欠損以外のゴア描写の例
(4)睾丸への哀歌
(1)現実的な観点からのヘッドショット
狙いにくい頭部が一撃必殺の急所という設定はリアルでもあり、ゲーム性とリアリズムが融合した例のひとつともいえる。ただし細かいことを言えば、銃弾が脳を貫通しても意識を保っていたり、脳の一部分を喪失するほどの重傷を負っても一命を取り留めた例はしばしばある。即時無力化という意味で真の急所といえるのは脳の指令を人体に伝える中継地点「脳幹」であり、ここを破壊されると人体の活動はすべて瞬時に停止する。
 緑色の部分が脳幹
緑色の部分が脳幹銃撃戦においてちっぽけな弾丸が脳幹に命中するケースは稀であるが、銃弾は見た目の貫通創よりも大きな損傷を人体に与えることに注意せねばならない。弾丸が人体を貫く際、その衝撃波によって貫通創は一時的に大きく膨らむ。これを「瞬間空洞」といい、ライフル弾など高い運動エネルギーを持つ弾丸の場合は瞬間空洞も大きくなる(なお貫通創そのものは「永久空洞」という)。
 瞬間空洞(Temporary Cavity)と永久空洞(Permanent Cavity)
瞬間空洞(Temporary Cavity)と永久空洞(Permanent Cavity) ゼラチンブロックを貫通する銃弾。瞬間空洞の膨張に注目
ゼラチンブロックを貫通する銃弾。瞬間空洞の膨張に注目この瞬間空洞が大きい(=衝撃波が強い)ほど貫通創周辺の内臓組織にもダメージが及ぶ。特に人体は大部分が水分であり、血液・体液を通じて衝撃波が伝播する。弾丸の命中箇所によってはこれによって中枢神経が破壊され死を招くことになる。ゆえに、頭部へ銃撃を受けて一命を取り留めるのは、あり得なくはないとはいえ奇跡に近いといえる(甚大な後遺症が残る可能性は非常に高いが)。
なおライフル弾などを頭部に受けた場合、瞬間空洞の膨張圧力によって頭蓋骨が内側から破壊されることがある。ゲームによってはヘッドショットで頭部が破裂したように消し飛ぶものがあるが、あながち荒唐無稽な描写とも言えない。
(2)ゴア描写へのこだわり
前述のような「頭部を粉砕するヘッドショット」描写を盛り込んだゲームは少なくないが、日本向けのローカライズでは「暴力による身体欠損」は真っ先に規制の対象になるため、その描写を削られるケースが少なくない。
最も顕著なのはXbox360の看板タイトルだった『Gears of War』(日本発売・2007)シリーズのそれだろう。1作目の日本語版はオリジナル版とほぼ変わらず「頭が吹き飛ぶ描写」を実現していたが、2作目以降はこれが削られてしまった。
 『Gears of War』(初代)のヘッドショット
『Gears of War』(初代)のヘッドショットこれに伴い「頭部を失った死体がゆっくり膝から崩れ落ちる」というモーションもなくなり、ただ後方に倒れ込むという簡素なものに差し替えられている。単体でみればおかしな表現とはいえないが、初代GOWを知るファンは「以前できたものがなぜ今はできないのか」と悲憤の涙に枕を濡らした。 なお1作目の日本語版も実はオリジナル完全再現ではなく、頭部が吹き飛ぶ際に脳が飛び散る描写が削除されている。ただし脳味噌そのものがあまり目立たない仕様だったため、特に日本のユーザーから不満が上がることはなかった。
こうした表現規制はもっぱら日本の販売会社による自主規制であり、気骨あるメーカーの場合はオリジナルを尊重してゴア描写にも手を加えないこともある。近年では『Fallout4』(2015)が忠実なローカライズを行っており、ヘッドショットでも頭部が砕け散るゴア描写を拝むことができる。
 『Fallout4』(日本語版)のヘッドショット
『Fallout4』(日本語版)のヘッドショットなお同作の疑似コマンドバトルシステム「V.A.T.S」は使用中にスローモーションがかかるため、これでヘッドショットを決めると脳や眼球が飛び散る様をじっくり眺められる。V.A.T.S関連の能力を強化すれば複数の敵に連続してヘッドショットを決めることもできるので、ビジュアル面に限っていえばFallout4こそ「脳天をぶち抜く愉悦」を最も味わえるゲームといえる。
(3)欠損以外のゴア描写の例
Fallout4のような例外はあるが、基本的に日本では欠損を含むゴア描写は採用されにくい(ゾンビ等の怪物はその限りではないが)。
そうした中で、欠損描写を用いず強烈なヘッドショット描写を実現していたのが『Sniper Elite:V2』(2012)である。この作品では敵に致命打を与える際の演出として「X-RAYキルカム」というものがあり、銃弾がヒットする瞬間に敵の頭蓋や脳が透け、それらが破壊される様をスローモーションで見ることができる。
 『Sniper Elite:V2』のヘッドショット(X-RAYキルカム時)
『Sniper Elite:V2』のヘッドショット(X-RAYキルカム時)見方によっては頭部が消し飛ぶよりもグロテスクな描写だが、「欠損」ではないため日本でも規制の対象にはならず、CEROの年齢区分でも“D”(17歳以上推奨)にとどまっている。
X-RAYキルカムは純粋に「人体破壊描写」にこだわった結果であり、日本市場を考慮して実装されたものではないが、暴力描写の可能性について日本のゲーマーにも考える機会をもたらしたのではないだろうか。
(4)睾丸への哀歌
上記のX-RAYキルカムによる演出は、ヘッドショットに限らず他の部位を狙った場合にも発生する。心臓等の臓器を撃ち抜く「バイタルショット」、眼球を撃ち抜く「デッドアイ」などが挙げられるが、その中で特に際立っているのが、男子の一番大切なものを撃ち抜く「ナッツショット」である。
 ナッツショット時のX-RAYキルカム
ナッツショット時のX-RAYキルカムいわゆる“金的攻撃”を取り入れたゲームは他にも例があり、シューターの分野でも基本プレイ無料のFPS『Combat Arms』(2009)がナッツショットを導入している。
 『Combat Arms』のナッツショット
『Combat Arms』のナッツショットSniper Elite:V2のナッツショットがこれらと一線を画しているのは、本来目にすることのない「内臓器官としての睾丸」の破壊をまざまざと描いた点である。白っぽくつるりとした――毛むくじゃらの外観とはまるで違うナイーヴな器官が無残に粉砕される様は、多くの男性プレイヤーの睾丸を縮みあがらせた。
睾丸を一撃される痛みは、異性には想像できないという点で女性の出産の痛みと比較されることが多い。だが産みの苦しみが子の誕生や母性の目覚めと不可分であるのに対し、睾丸の痛みは何も生まず、何かが始まることもない。村上春樹をして「じきに世界が終わるんじゃないかというような痛み」(『1Q84』より)と言わしめた、虚無的な苦痛があるだけである。
そしてこの苦しみははたから見ると――同じ男性の目からも――滑稽に映る。人間の肉体が負うあらゆる痛みの中で、睾丸の痛みほど同情を得にくいものは稀であろう。ナッツショットも「面白要素」として扱われているが、仮に女性の敵キャラに同様の要素が盛り込まれたら、どれほどの非難が巻き起こるか考えてみるとよい(なおSE:V2に女性の敵は登場しない)。
男性生殖器でも陰茎は時に“男の象徴”とされ、その立派さを誇る文化は世界のどこにでもある。だが、睾丸はそのように誇示されることはない。子孫を残すという意味では最も重要な役割を担っているものの、どこまでもつつましく、脆弱で、庇護されるべき存在である。にも関わらず笑いを取るために痛めつけられる現状は、睾丸の身になって考えるといささか不憫である。
なおSMのプレイには「睾丸責め」なるジャンルがあるというが、まったくもって理解不能な話である。
関連:【芋スナ】 【FPS】
■ホワイト・ジャズ
(小説)

ジェイムズ・エルロイ「暗黒のLA四部作」最終作。センテンスごとにブッた切られた独特の狂気文体を全開にして突っ走る、暗くて熱い暗黒小説。
「暗黒のLA四部作」はいずれも緻密な構成からなる謎解きが仕込まれており、物語の全貌を理解するのに幾度か読み返す必要がある(少なくとも管理人はそうだった)。それに加え、このホワイト・ジャズはこの特殊な文体のため、単に流れを追うことすら困難になっている。
ただ、この文体は焦りと苛立ち、追い詰められた恐怖と狂気によってズタズタになっていく主人公の思考を実によく表していると感じる。
なお、この物語は最初と最後に主人公・クラインの独白があるのだが、これが非常に印象深い。プロローグのみをここに記しておく。
あるのは思い出そうとする意思だけだ。葬られた時間/熱に浮かされた夢――目を覚ますと、忘れるのが恐ろしくて手を伸ばす。写真の中の女は年をとらない。
LA、1958年秋。
新聞=黒い点の連なり。名前、事件――いずれ劣らず残忍で、ひとつにつながろうともだえている。時は下って――話はいまだにばらけたままだ。名前の主たちは死ぬか、でなければ、あまりの罪深さに口を閉ざす。
おれは年老いた。忘れるのが恐ろしい。
無実の人間を殺した。
聖なる誓いを裏切った。
恐怖に乗じて儲けた。
熱――燃えていたあの時。音楽に身を任せよう――ぐるぐるまわって、落ちていくのだ。
関連:【暗黒のLA四部作】 【サンダーライン・ジョンソン】 【ハレルヤ、おれは飛べる!】